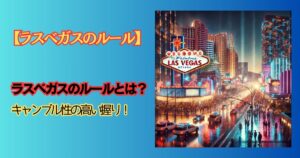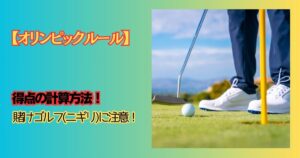ゴルフの新ルールでドロップの変更点を理解していますか?
2019年に変わった「膝(ヒザ)の高さからのドロップ」や「救済エリア内に止める条件」など、トラブル時の基本ルールを解説します。
ペナルティエリアに入ったときのストロークと距離の救済や、ペナルティエリア内でのアンプレヤブルのルールなど、ゴルフ初心者にわかりやすく紹介しますので、基本ルールを覚えましょう。
- 新ルールでのドロップ方法とは?【ゴルフ】
- ストロークと距離の救済の基本ルールと手順を解説!
- ペナルティエリアでのストロークと距離の救済と注意点
- アンプレヤブルの対応と選択肢
新ルールでのドロップ方法とは?【ゴルフ】

ゴルフの新ルールでは、ドロップの方法が大きく変更されました。
最も重要な変更点は、従来の肩の高さからではなく、膝の高さからボールを落とすことが義務付けられた点です。
ドロップ方法の変更により、ボールが救済エリア内に止まりやすくなり、プレー進行がスムーズになります。
救済エリアから出た時など、正しい救済方法を理解しておけば、コース上で迷いがなくなり自信を持ってプレーできます。
ドロップ位置と膝(ヒザ)の高さのルール変更
2019年のルール改正以降、ドロップは膝の高さから行うことが正式に決まりました。
この変更は、プレーの公平性と効率性を高める重要な改善点です。
以前は肩の高さからドロップを行っていましたが、ボールが予想外の方向に転がる場合がありました。
膝の高さからのドロップには、いくつかの重要なポイントがあります。
最初に膝の位置とは「膝から地面までの距離」という意味で、立ったままの状態での膝の高さからドロップします。
膝を曲げる必要はなく、手からボールを単純に落とせは問題ありません。
投げたり、回転をかけたりといった誤った動作によるドロップは、ペナルティの対象になる場合もあります。
救済エリア内にボールを止める条件
ドロップしたボールは、必ず決められた「救済エリア」内におよぶ必要があります。
救済エリアとは、基準となるポイント(例:ペナルティエリアの縁やニアレストポイント)から1クラブレングス以内の範囲です。
救済エリア内にボールが止まらなければ、もう一度ドロップが必要となります。
ドロップをインプレーになる条件として、以下のポイントを覚えておいて損はありません。
- 膝の高さから落とす
- 最初に落ちた場所が救済エリア内であること
- 救済エリア内にボールが止まること
もし2回落ちても救済エリア内に止まらない場合は、2回目に落ちた場所にボールをプレースします。
例えば、池にボールが入った場合、ペナルティエリアの縁の地点から後方(ホールとニアレストポイントを結ぶ)の線上を引きます。
その線上の好きな地点を選ぶ「後方線上救済」を選択する場合、選んだ地点から1クラブレングス以内の救済エリアにボールをドロップします。
2023年以降のルール改正により、後方線上救済に限り、ホールに近づいても1クラブレングス以内であれば許められるようになりました。
ほかの救済方法(ラテラル救済やストロークと距離の救済)では、ホールに近づくことは、許されません。
ストロークと距離の救済の基本ルールと手順を解説!

ストロークと距離の救済とは、ゴルフにおける最も基本的な救済方法です。
この救済方法を理解すれば、ペナルティエリアやOBなど、さまざまなトラブルに対応できます。
基本的には「1打罰で元の場所から打ち直す」というシンプルなルールです。
しかし実際のコースでは、状況判断や正しい手順が求められます。
ストロークと距離の救済について、正しく理解して、プレー中の判断にも活かしましょう。
ストロークと距離の救済とは?
ストロークと距離の救済とは、1打のペナルティを加えて、直前に打った場所から再プレーする方法です。
この救済は、ボールが見つからない場合、OB(アウトオブバウンズ)になった場合、あるいはプレーヤーが自主的に選んだ場合に適用されます。
例えば、ティーショットがOBになった場合、次のショットは2打目ではなく3打目として、ティーイングエリアから再プレーします。
前進からのショットがペナルティエリアに入った可能性があるときも、元の位置から1打罰を加えて打ち直せます。
この救済方法のメリットは、どのような状況でも適用できる点です。
同様に、ほかの救済方法が使えない難しい場面(急な坂や藪の中など)でも、ストロークと距離の救済を選択すれば対応できます。
ルールも明快であるため、初心者でも安心して実践できるでしょう。
実際のプレー中、ボールが林の中で気付いて「このままでは次のショットが難しいそうだ」と感じた場合も、元の場所から打ち直すことができます。
もちろん1打のペナルティは加わりますが、リスクを回避する手段として再プレーを選ぶのも判断です。
適応する場面と具体的な手順
ストロークと距離の救済が適用される主な場面は、以下の通りです。
- ボールがOBとなった場合は、必ずストロークと距離の救済を受けます
- ボールを3分以内に見つけられなかった場合も、ロストボールとして同様の処置が適用されます
具体的な手順としては、1打のペナルティを加えて、元のショットを打った場所から再プレーを行います。
ティーショットであれば、ティーイングエリアのどこからでも打てますが、コース内からのショットの場合は、元の位置を特定する必要があります。
ただし、池越えのショットでボールが、水に入った場合を想定してみましょう。
このケースでは、元の場所から打ちストロークと距離の救済を選べます。
具体的には「ペナルティエリアに入りましたので、ストロークと距離の救済を適用します」と宣言し、1打罰を加えた後、元の位置に戻り再プレーします。
ペナルティエリアでのストロークと距離の救済と注意点

ゴルフでペナルティエリアにボールが入った時、ストロークと距離の救済は基本的な選択肢の一つです。
ペナルティエリアでは、ストロークと距離の救済以外にも、さまざまな救済方法があります。
ラウンド中、ペナルティエリアにボールを入れた際には、自信を持って対応できるようにルールを覚えましょう。
ペナルティーエリアで選べる救済オプション
ペナルティエリアでは、主に3つの救済オプションから選択できます。
どの救済方法も1打罰が課されますが、状況によって最適な選択は異なります。
- ストロークと距離の救済:直前に打った場所から再プレーする方法
- 後方線上救済:ホールとニアレストポイントを結んだ後方線上にドロップする
- 赤杭のレッドペナルティエリアではラテラル救済も選択が可能
※(ペナルティは課されないが、あるがままに打つ選択肢も存在します)
上記のラテラル救済は、レッドペナルティエリア縁のニアレストポイントから2クラブレングス以内の救済エリアにドロップする方法です。
多くのゴルファーが、グリーン手前の池越えショットで池ポチャを経験しています。
その後、ラテラル救済を選択し、2クラブレングス以内にドロップし、打ち直しでグリーンにオンさせた経験があるでしょう。
ラウンド中にレッドペナルティエリアへボールが入ってしまった場合は、3つの救済方法を思い出し、それぞれのメリット・デメリットを考慮して、成功確率の高い方法を選びます。
後方線上の救済とラテラル救済の違い
後方線上救済とラテラル救済は、どちらもペナルティエリアからの救済方法ですが、ドロップする位置と適用される状況に明らかな違いがあります。
後方線上救済は、ボールがホールとニアレスポイントを結ぶ後方線上の任意の地点にドロップする方法です。
ラテラル救済は赤杭(レッドペナルティエリア)の場合のみ適用可能であり、黄杭のペナルティエリアでは使用できません。

アンプレヤブルの対応と選択肢

アンプレヤブルとは「プレーできない」という意味であり、ボールが木の根元や茂み、深いバンカーなど、プレー継続が困難な状況に適用される救済方法です。
1打のペナルティが課されますが、難しい状況から抜け出すための有効な選択肢となります。
ゴルフ初心者の場合、無理に打ち続けてミスするよりも、アンプレヤブルを活用するほうが、結果的にスコアを崩さずに済むかもしれません。
アンプレヤブルとは?
アンプレヤブルとは、プレーヤー自身が「このボールはプレー不可能だ」と判断した時に宣言できます。
重要なのは、同伴者の判断でなく、自らの判断によって宣言できる点です。
典型的な状況としては、ボールが樹木の根元、岩や壁の近く、深いラフや茂み、あるいはバンカー内で非常に悪いライの場合などが該当します。
アンプレヤブルを宣言する場合は、自分がプレー不可能と判断し、1打罰を受け入れて救済措置を選択するでしょう。
ボールがペナルティエリア内にある場合は、アンプレヤブルは適用されず、ペナルティエリアの救済方法を優先して選ぶ必要があります。
アンプレヤブルの状況判断
アンプレヤブルを活用するかどうかは、以下を参考に判断しましょう。
- 現在のボール位置からショットできるかどうか
- 無理なショットでないか?(クラブ破損、怪我などのリスクがあるか)
- 3つの救済方法のうち、ショットの難易度は?
- どの救済方法が、距離のロスをなくせるのか?
- コース戦略の中で、どの選択が最適なのか?
プレーできない状況に遭遇したら、アンプレヤブルを活用を検討しましょう。
プレーの状況と救済方法を踏まえ、メリット・デメリットを比較した判断が必要です。
まとめ
ゴルフの新ルールでは、従来の肩の高さから行うドロップが膝の高さに変更され、救済エリア内にボールを止めるための条件も明確になりました。
ストロークと距離の救済は、ペナルティエリアでの処置やOB時などに活用できる基本的なルールです。
基本的なルールを守れば、コース上でのトラブルにも冷静に対応できます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。